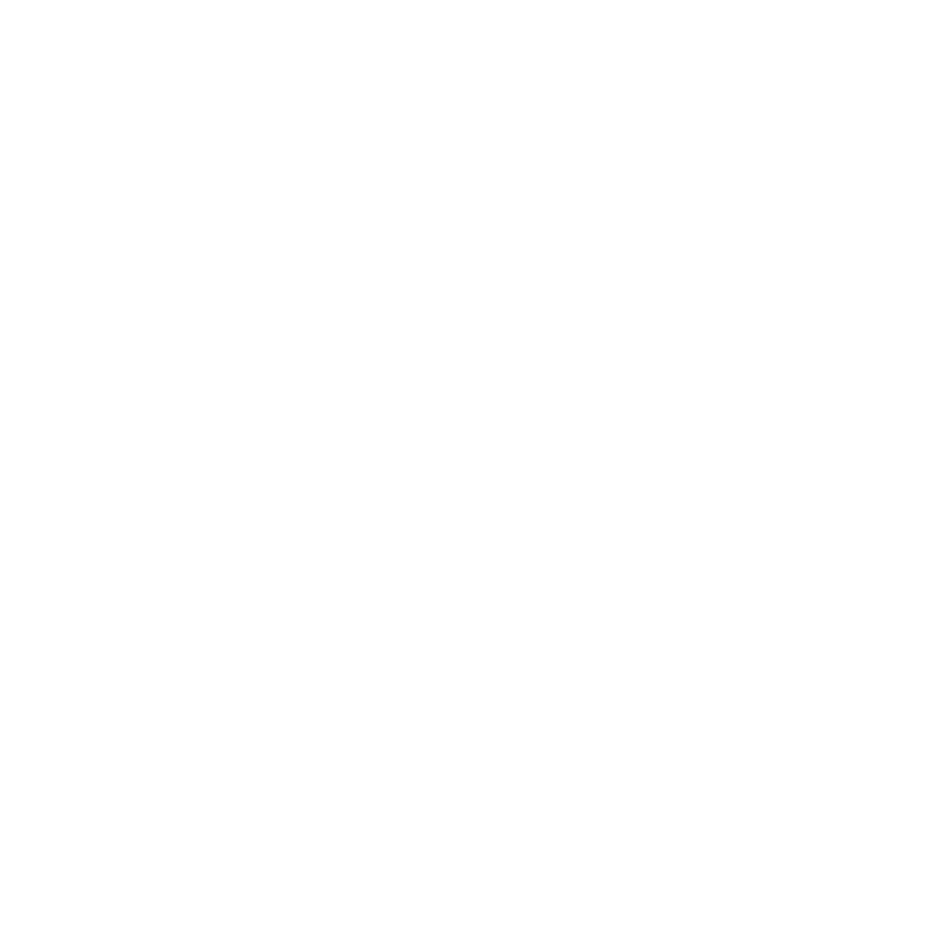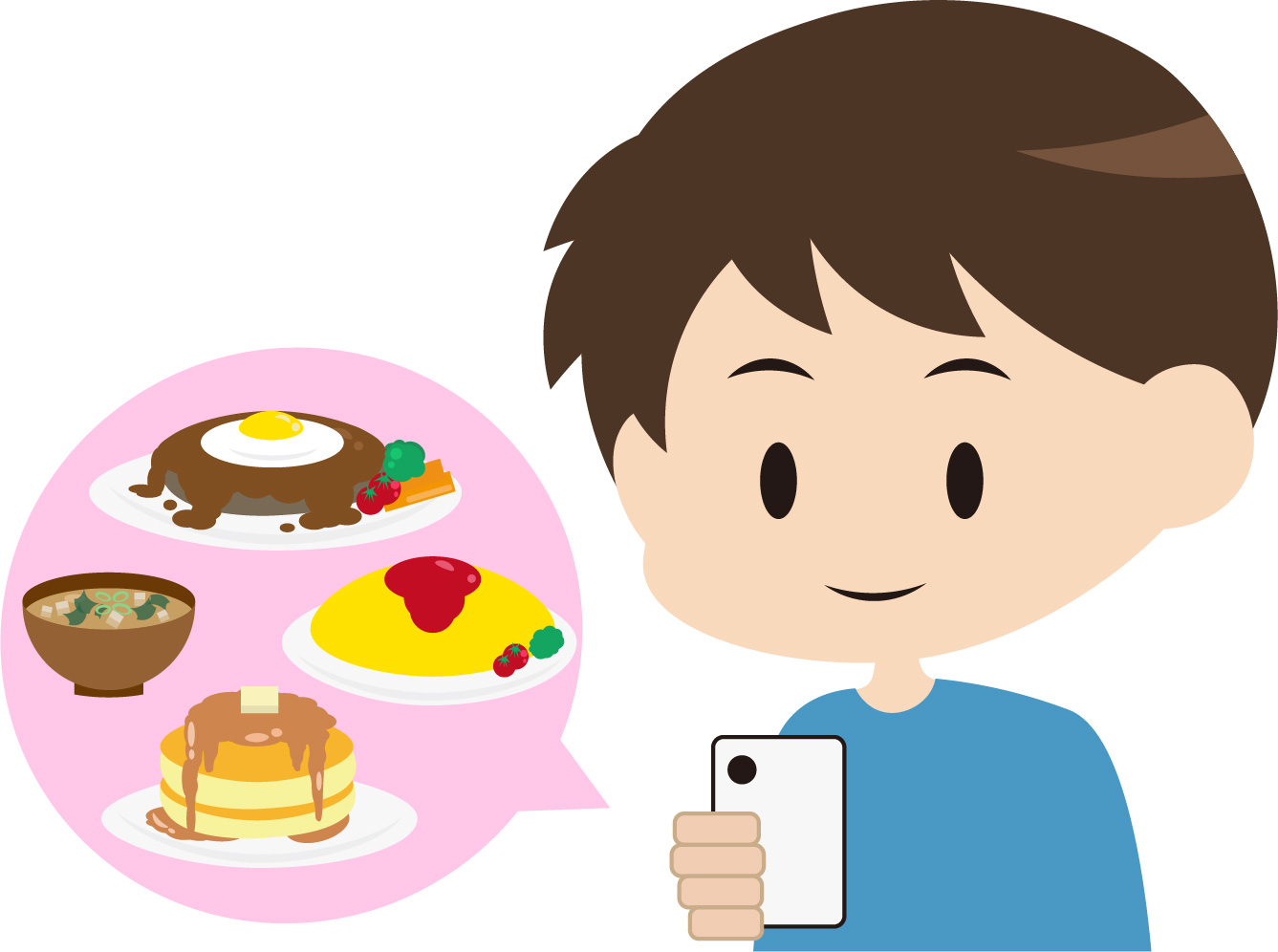■フードデリバリーはもう生活の一部
最近、フードデリバリーを使う頻度がグッと増えた人も多いと思います。
仕事で疲れて帰ってきた夜や、雨の日、ちょっと贅沢したい休日。
スマホをポチポチするだけで、いろんなジャンルの料理が家まで届くって、本当にありがたいですよね。
昔は「出前」と言うと、寿司かピザくらいしか選択肢がなかったでしょう。でも今は違います。
カレーもラーメンも、ヴィーガン料理やエスニック、韓国料理まで、実にバリエーション豊富です。
和洋中すべてそろっている上に、地元の小さな個人経営のお店の味を気軽に楽しめるのも、今のフードデリバリーの魅力です。
アプリもどんどん進化しています。Uber Eats、出前館、Wolt、menuなど、多くのサービスが競い合うように機能性を高め、操作も簡単で直感的。
お気に入りの店や料理を保存できたり、到着予定時間をリアルタイムで確認できたりと、まさにストレスフリー。
「今日はもう作らなくていいか」と思わせてくれるほど、便利さが生活に溶け込んでいます。
■フードデリバリーを支える配達員の存在
そして忘れてはならないのが、私たちの代わりに走り回ってくれる配達員の存在です。
晴れの日ばかりではありません。強風、雪、猛暑、どんな天候の日でも、指定した時間に料理を届けてくれる。
それは単なる「仕事」の枠を超えて、ちょっとしたプロフェッショナル精神すら感じさせます。
実際、フードデリバリーの現場では、配達員が道に迷わないよう最新のGPSが導入されていたり、効率よく複数の注文をまとめて運べる仕組みが整えられていたりと、裏では相当な工夫がされています。
■フードデリバリーを利用する人々
ただ、こうした便利なサービスには、やはり利用者側の配慮も欠かせません。
たとえば、玄関先での受け取り時に一言「ありがとうございます」と伝えるだけで、配達員の気持ちも少し軽くなるかもしれません。
受け取ったあとの評価やチップ制度(任意ですが)なども、相手への感謝を表す一つの方法として見直されつつあります。
最近では「置き配」などの新しい受け取りスタイルも定着しつつありますね。
対面せずとも料理を受け取れるので感染症対策やプライバシーの面でも安心です。
■フードデリバリーの浸透
フードデリバリーがここまで浸透した背景には、コロナ禍での外食制限や、テレワークの広がりも影響しています。
それまで「特別なときに使うもの」だったデリバリーが、「日常の延長線」に移ったとも言えるでしょう。
一方で、便利さが当たり前になりすぎると、感謝や配慮の気持ちが薄れてしまうこともあるかもしれません。
「ボタンひとつで食べ物が来る」のではなく、「誰かが作り、誰かが運んでいる」。
このシンプルな事実を、たまには思い出してみてください。
■さいごに
フードデリバリーは、これからも多くの人にとって必要不可欠な存在であり続けるでしょう。
だからこそ上手に、そしてちょっとだけ優しく付き合っていきたいですね。